クレジットカードの歴史とこれからについて
公開日:2018年03月26日
更新日:2024年12月03日
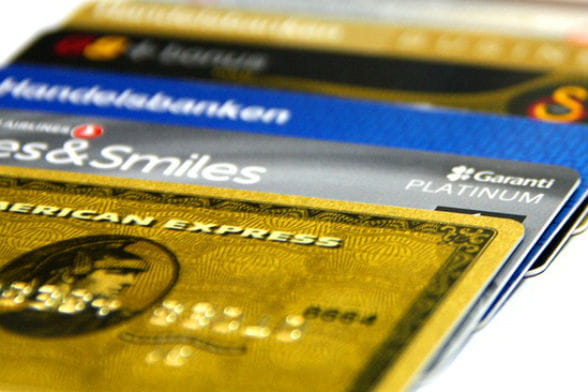
社会人なら財布の中に1枚や2枚は入っているのが当然になっているクレジットカードですが、このシステムはいつ、どのような過程を経て作られたのでしょうか。
そして今後クレジットカードはどのように進化していくのでしょうか。
ここではクレジットカードの歴史についてご紹介いたします。
クレジットカード誕生のきっかけになったこととは
世界で初めてクレジットカードが誕生したのは、第二次世界大戦後のアメリカだったと言われています。1950年、実業家のマクナマラと弁護士のシュナイダーがニューヨークで食事をしていた時、マクナマラは家に財布を忘れてきたことに気付きます。
マクナマラはあわてて妻に電話し、レストランに現金を届けてもらいますが、彼らはこれをきっかけに「手持ちの現金がなくてもツケで食事ができるクラブがあればいいのではないか?」というアイデアを思いつきます。それが現在、日本を含め世界中で展開しているクレジットカード会社「ダイナーズクラブ」を立ち上げるきっかけになったそうです。
日本においても、クレジットカードというシステムではなかったものの、クレジット(信用)を担保に手持ちの現金がなくても買い物ができるやり方は古くから存在しました。例えば江戸時代、呉服屋では高額商品なゆえにツケ払いで商品が購入できたと言います。さらに商品の支払いを一括で行うのではなく、月賦払いや割賦払いにすることも行われていました。
クレジットカードの歴史
アメリカで誕生したクレジットカードが日本に広まったのは1960年代になります。カードが広がるきっかけとなったのは、1964年に開催された東京オリンピックです。多くの外国人観光客の来日に合わせて、すでに海外では当たり前のこととして利用されていた「クレジットカード払い」のシステムを日本にも普及させる必要が生じたのです。
そのため1960年、日本最初のクレジットカード会社である「日本ダイナーズクラブ」が設立されました。日本ダイナーズクラブは、それまで紙製だったクレジットカードを現在の仕様となるプラスチック製のカードに変更するなど、システムの改良に取り組みます。
また、クレジットカードの普及に大きな役割を果たしたのが、百貨店業を営んでいた丸井でした。丸井は「クレジット」という言葉を初めて使い、それまで買い物は現金一括払いが当たり前と思っていた一般の消費者に、クレジットカードを使う事により分割払いでモノを買うという新しいスタイルを提案しました。ただ、当時はクレジットカードに引き落とし機能は付いておらず、カード利用者は月々の支払いを店頭に出向いて行わなければなりませんでした。
クレジットカードの歴史のこれから
今やすっかり世の中に浸透したクレジットカード。今後はいったいどのような進化が考えられるのか、2つの側面から解説します。
ICチップの義務化
2020年の東京オリンピック開催に向けて、決済端末のクレジットカードICチップ対応が義務となりました。現在クレジットカードの主流である磁気ストライプ方式はスキミングなどの被害に遭いやすいため、ICチップを導入することでカードのセキュリティを強化するのが狙いです。
デビットカードの普及促進
クレジットカードとよく似たカードにデビットカードがあります。デビットカードは銀行などの金融機関が発行するカードで、使った瞬間に預金口座から利用代金が引き落とされます。クレジットカードの特性である、後日のツケ払い、割賦払いなどの機能はありません。<
デビットカードの利用には審査が無く、15歳以上で預金口座があれば誰でも利用可能です。また、その場で支払いが完了しますので、ATMに行く時間を省けますし、ATM手数料も節約できます。
デビットカードは海外では広く流通していますが、日本ではまだそれほど普及していません。そのため近年カード会社は今後の伸びしろに期待して、デビットカードの普及に力を入れています。
まとめ
クレジットカードが世の中に誕生して70年近く。支払い方法としてすっかり定着した感じがありますが、それでも世界的にみると日本人のカード利用率はまだまだ低いと言えます。今後、ますますセキュリティを強化していく必要もあり、クレジットカードの新たな形が模索されています。
また、デビットカードや電子マネーと端末を共用するなど、うまく共存することでキャッシュレス決済がより浸透していくことが期待できます。









