ECのコンセプト、ユーザビリティ、機能と選択肢
~ECの成功のための考え方~
公開日:2025年04月21日
更新日:2025年04月21日

ECの立ち上げや成長のために考えるべきは、どんなことで、どう意味を持ち、ECビジネスやECサイトを形作っていくのでしょうか。ここでは、ECのコンセプト、ユーザビリティ、決済を含む機能と選択肢を使っての考え方を解説していきます。
-
[目次]
- ECを始める際に大事なこと
コンセプトとは
消費者をなめてはいけない
コンセプトに合わせてECビジネスとサイトを作っていく - 機能や選択肢とは
機能や選択肢のレベル感 - 具体的に機能や選択肢を考える前に。ユーザビリティとは何か
ユーザビリティとは
ユーザビリティに独自性や差別化はいらない
ユーザビリティ改善と機能や選択肢の導入は違う - 決済方法の具体的な選定
実績や調査から決めていく
顧客のニーズ、商材、販売方法から決める
人気の決済方法を利用する
成長フェーズ等で、好ましい機能や選択肢は違う - 決済方法をいくつ提供するか
選択肢の数とユーザビリティ
サイト上の説明文 - 特に決済フローには、独自性や差別化は不要。それよりも
顧客の利用の多い方法を上位に、そして、デフォルト化する
とはいえ、意図的な表示の仕方も要検討 - 機能や選択肢の追加、終了
機能や選択肢の終了
サービスアップの流れで顧客の支持を生み出す
サイトオープン時に、機能や選択肢でもリスクはとらない - まとめ
- ECを始める際に大事なこと
ECを始める際に大事なこと

筆者は、ECに関わり始めてすでに30年近く、大手EC 3社の立上げや事業責任者の経験を経て、現在はコンサルタントとして、構想や戦略に関し、数多くの中小~大規模の事業者の支援を行ってきました。そして、起業支援の一環としても月に数件以上のECの相談を受けています。そのながれで、構想から具体的な運用までECの作りやインフラ等に多く携わっています。
ECを立ち上げる際、そして、どう成長させるかを考えるとき、なんとなく始めるでは、結局はうまくいきません。特にある程度の規模を目指す場合は顕著です。しかし、いまだに実に多くの事業者が、EC市場が伸びている、同業がやっているからという理由で開始しています。早く〇〇円規模にしたい、△△店と競合できるようにしたい等を、ECのコンセプトとして説明されることも多々あり、そんなとき、筆者は本気でないならやらないほうがよいですよ、と辛口にお話することにしております。
世の中の趨勢(すうせい)に合わせ、ECに取り組むというのは、きっかけとしてよいことですが、実際に始めるには、まずは、どんなECであるかを考えるべきです。実店舗では当然考える、どんなお店にするかです。こんなことを考えずに始めてもうまくいっている事業者もあります。しかし、長くECをやっている立場からいうと、まぐれでしかありません。特にある程度以上の規模をめざすのであれば、うまくいく確率を上げることが必要でしょう。ありきたりの言葉でいえば、成功のためにちゃんとコンセプトを考えておきましょうということです。
コンセプトとは
実際、コンセプトでも、構想でも、テーマと呼んでもいいのですが、何を意図しているかというと、筆者がよく使う表現であれば、「自社が行うべき、あるべきECの姿」をちゃんと考えましょうということです。そして、「『どんな(提供)価値』を『どんな人』に『どのように提供』して『どんな体験』をして欲しいかという一貫した考え」です。そして、細く緻密な計画はなく、上の要素が入った、ちゃんと自分事で考えられた大きな考えです。
コンセプトに合うかが何かをするときのベースの基準となります。ECに関するすべての決定、活動の根底となる考えですので、これから機能や選択肢等を導入する際はコンセプトに合っているかどうかを検証すれば決定しやすくなります。ところが、コンセプトがないと、つどつど、何に対して適しているか等根底レベルから個別の検討する必要がでてきて、時間もかかりますし、ぶれていきます。
では、どんな考えがよいかと言われても、会社毎に違いますので正解はありません。一つ言えるとしたら、顧客が体験するだろうことに向かい合って、ちゃんと考えて、徹底できていれば、どんなコンセプトと言われているものも正解です。
消費者をなめてはいけない
筆者が、Webを含めメディアやチャネルを運用していて、だんだん感じるようになったことは、消費者は、事業者側のいい加減な/安易な考えを「見透かす」ということです。企業の「こんなものでいいや」、ユーザーには、このあたりの品揃え、機能や選択肢を提供「しておけばいい」といった感覚で用意されたものをです。成長に時間がかかったり、そして、明確なご意見もないのに、停滞し始めたり、急にアクセス、コンバージョン、売上が減るということがあります。これは、サイトの作り、機能や選択肢の一つ一つの良し悪しではなく、その後ろにある、「一貫した考え」に沿っているか、「あるべき姿」に合っているかに起因します。これは、もともと筆者が店舗等で思っていたものですが、ECでも強く感じたことです。品揃え等はもちろんのこと、サイトのトンマナ、取り入れた機能の種類、コンテンツや運用の質等で顕著に現れてきます。
コンセプトに合わせてECビジネスとサイトを作っていく
ECビジネス、ECサイトを構築、改善していく際には、様々な検討、選択をしていく必要があります。品揃え、プラットフォーム、サイトの色合い、トンマナ、フォント、画像の質、機能、サービス、配送方法、配送料、支払い方法など、本来は、すべての選択に意味があり、コンセプトを実現するためのものです。言い換えれば、コンセプトに合っているかどうかを検討し、取り入れるかどうか決定します。
しかしながら、提案型のECなのにコンテンツが見つからない、商品説明が短い、価格追求型なのにカスタマイズのオプションがやたら多い、働いている人向けなのに代引きがメインの支払い方法、シニア向けなのにデザイン優先で文字が小さい等、とんちんかんな事業者をよく見かけます。そういうちぐはぐなことに、消費者は気づきますし、または、無意識に使いにくいと感じ、そのECを利用しなくなります。せっかくコンセプトがあっても、徹底できなければ意味はありません。
機能や選択肢とは

ここでは、【機能】を、リコメンド・上級の検索・ボット・AIモデル・サイズ提案等のサイト上の仕組みやサービスを実現するもの、【選択肢】を、配送・ラッピング・決済等の各方法/オプションのことを指し、すなわち「顧客のできること」を増やすものとしております。
機能や選択肢のレベル感
それでは、どんな機能や選択肢を取り入れればよいのでしょうか。いくつかのレベル感で分類してみると下記のようになります。
- 基本的な機能と選択肢
これらがないとサイトをオープンできないようなもの - 標準となっている機能と選択肢
競合サイトや同業のほとんど/多くで採用されていて、スタンダードとなっているもの - まだマイナーな機能と選択肢
いくつかのサイトで採用され今後広がっていくと思われるもの - 自社独自の機能と選択肢
他サイトでは採用されていない、また、ほとんど採用されてないが、自社にとって有効だと思われるもの。売上には、すぐに貢献しないかもしれず、また、社内のリソースをかなり使うかもしれないもの
機能や選択肢を検討する際には、コンセプトに合っているかを踏まえたうえで、これらのどれにあたるのかを考え、そのときどきの会社の姿勢、成長フェーズにも合わせます。立ち上げ時や安全重視の姿勢が顕著な際は①②のみで、成長志向が高いときは③等の積極姿勢で、そして、顧客や業界に対して、先進的な取り組みをしていると思われたいときは④等も採用の可能性が高くなると考えられます。
具体的に機能や選択肢を考える前に。ユーザビリティとは何か
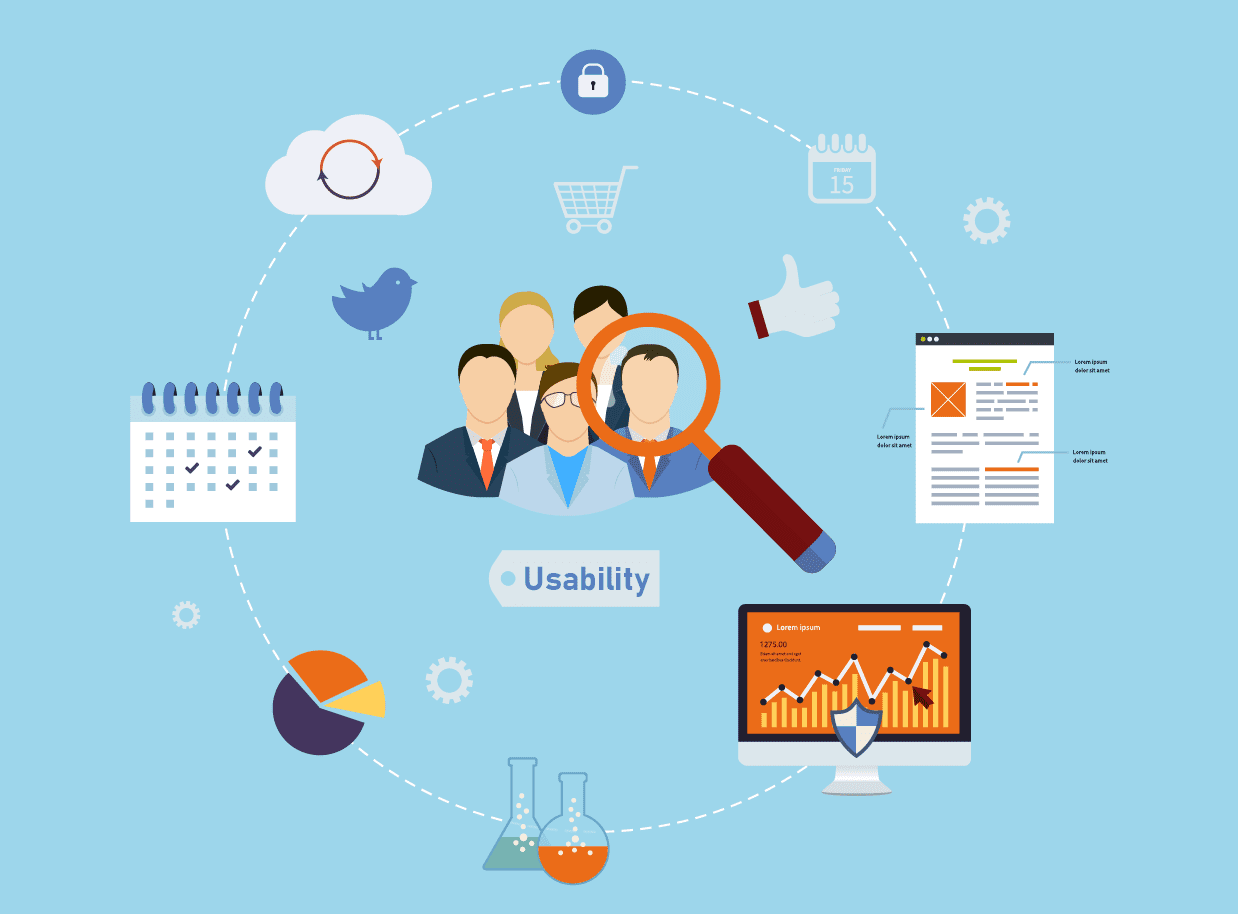
ユーザビリティは、「機能と選択肢」を充実させると向上するとよく誤解されますが別ものです。そして、コンセプトうんぬんの前に知っておくべきことでもあります。
ユーザビリティとは
基本的にユーザビリティは、シンプルでわかりやすいこと。Webユーザビリティの最も有名な教科書として世界中で長く使われているSteve Krugの「Don’t Make Me Think(ウェブユーザビリティの法則)」では、
ユーザビリティ≒「次にどうすればいいかを、直感的にわかるようにする」
を一つの考えとしています。「わかるようにする」という考えと、「顧客のできること」を増やすための機能と選択肢とは別物だとはっきりすると思います。
そして、Webリテラシーの低いユーザーを狙うことがうたわれたコンセプトのサイトであれば、ユーザビリティ自体が、重要なコンセプトの実現要素となります。
ユーザビリティに独自性や差別化はいらない
ユーザビリティの意味合いでは、どんなに優秀な作りでも、人々が慣れていないため、戸惑ってしまう作りは好ましくないとなります。例えば下記の2つです。
- 他の多くのサイトと違う、また、独自すぎる使い勝手や仕様はNG
普及して、同じセグメントのECのユーザーが使い慣れているものは、本当は問題があっても、使いやすくユーザビリティがよいということです。フローやレイアウトは、奇をてらわず、他サイトでもよく使われている流れ、配置が好ましいという意味です。
EC創世記に、ECの利用が進んだ理由の一つに、多くの事業者が、
サイト上での主動線を「検索⇒商品一覧⇒商品詳細⇒カート⇒ログイン⇒購入/決済フロー」と想定して、
購入/決済フローを「カート⇒ログイン⇒配送方法⇒支払い方法⇒確認⇒確定」とした
ということがあります。当時は、他のフローもあったのですが、多くがこの流れに収束され、利用者が悩まず、使い方での離脱が減り、ECでの買い物が普及したと言われています。一説には、成功していたアマゾンがこの流れを採用していたので、他社がまねたため、という話もあります。要は、他のサイトと違う購入フロー等は、顧客にとってわかりにくく、すなわち使いづらく、離脱の原因となります。この観点からだと、よほどのわかりやすくなる改善以外は、やらないほうがよく、横並び的に他サイトに合わせたほうがよいということです。しかし、それを踏まえても、コンセプトの実現や他のメリットのために、使い勝手が違っても、あえてやるという判断もあります。 - 頻繁な使い勝手の改修、変更はNG
サイト開始後、どんなによい改善でも、既存のサイトを変更した場合、一時的に使い勝手が悪いと判断され、コンバージョンが低下したり、離脱が増えることがあります。そして、不満やクレームが発生することもあります。改善の意図が正しければ、時間とともに顧客に受け入れられ、以前よりコンバージョンが増え、離脱は減ってきますが、頻繁なサイトの変更、リニューアルは、いくら改善であっても、避けたほうがよいと考えられます。
ユーザビリティ改善と機能や選択肢の導入は違う
ユーザビリティ改善目的の機能を除いては、基本的に機能や選択肢を増やしてもユーザビリティは改善されません。さらに言うと、機能や選択肢を増やすと、サイト上の必須以外の要素、情報が増えるため、ユーザビリティ自体は低下します。改修、機能や選択肢の追加で得られるメリットとマイナス要因のバランスを評価して決めていくしかありません。
決済方法の具体的な選定
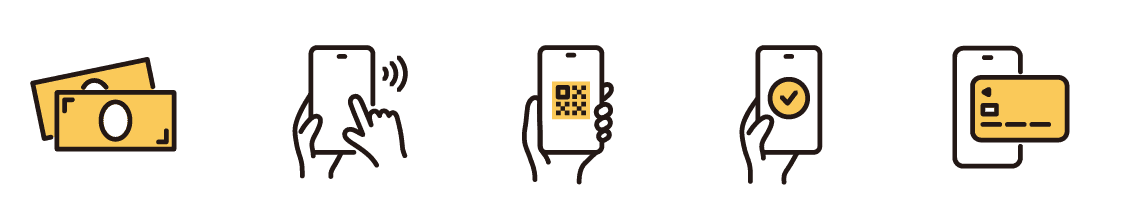
自社の顧客にあった選択肢、必要な選択肢数は、どう考えるべきでしょうか。調査の上、いくつかの要件から決めていきます。
実績や調査から決めていく
すでにECを行っている場合、そして、今後もターゲットの顧客層を変える予定がない場合は、既存の利用をベースに選定し、検討していきます。新しい支払い方法等が登場し、支持され始めているのであれば、自社の顧客層、商品カテゴリーに対し、どのくらい利用されているかを調べたうえで採用を決めます。
新規にECを始める場合は、実績がないので、新しい支払い方法等の追加を検討するときと同じように調べる必要があります。様々なリポートや専門メディアの記事等を集め、他社サイトの支払い方法のベンチマーク等が最低限の調査になるでしょう。自社が実店舗など別メディア/チャネルで同商品を販売している場合は、その実績がある程度参考となるかもしれません。ただ、まったく同じということは、ほぼないようです。
決済代行会社は、これまでの取り扱いから大まかなカテゴリーや顧客層での決済方法毎の利用状況をある程度把握しているはずですので、アドバイスをお願いするのが、選定の際のもっとも精度の高い情報となると思われます。これは物流、配送等の選定でも言えることです。筆者がECを含む新規事業をうまく立ち上げてこられたのは、パートナー/ベンダーから学び、入り込んで一緒に手を動かしてきたからです。筆者の過去の部下にも、支援先のスタッフにも同じことをすすめています。
顧客のニーズ、商材、販売方法から決める
筆者が以前かかわっていた会社では、根強いコレクター顧客がいました。価格をあまり気にせず注文されるのでとても優良顧客でしたが、クレジットカードや代引き以外の支払を強く要望されていたため、開設後、急遽、コンビニ払いを導入しました。理由は様々ですが、クレジットカードを好まない/持っていない顧客層もある程度いますが、購買力とは別のケースもありますので捨てがたい検討案件となりました。
別の会社では、コラボ商品のような数量限定の人気商品の販売が多く、即時決済ではなく、振り込み等を利用することは、入金確認までの期間は注文が確定できず、また、そのままキャンセルとなる可能性もあるため、事業者にとって機会損失となるし、他の顧客にフェアではないということで、商品毎に決済手段を制限していました。高額な商品の場合は、金額制限のない銀行振り込み等の方法が適しています。商品毎の設定が必要な販売方法は、顧客にもわかりにくくなりますし、運用が煩雑になるので避けたいところです。しかし、逆にこのように細かく手を入れることによって、ちゃんと考えて販売しているECという評価を受けることもありますし、ロイヤル顧客が多いECでは比較的支持されています。
人気の決済方法を利用する
対象顧客に人気の決済方法をウリにする場合は、商品詳細ページのカートボタンの周辺に「〇〇利用可」と記載する等も有効です。特に決済会社がキャンペーンを実施しており、広く告知されていたり、その特典がユーザーに魅力的であれば、活用しない手はありません。トップページの告知エリア、ページ共通のプロモーションスペース等でも訴求できます。ポイントアップ、キャッシュバックなどは、支払い方法によくある特典で、送料無料と同じように、注文を躊躇しているとき背中を押すことや、注文額の増加に大きく貢献します。ただし、コンセプトを邪魔しないような表現、そして、シンプルでわかりやすく記載することがユーザビリティ的には重要です。
購入フロー内でもフレキシブルな変更ができるのであれば、ある期間、対象の支払い方法を一番上や目立つ場所に配置したり、デフォルトにしておくという手法もあります。しかし、慣れている顧客には、違和感を与え、事業者側の意図が見え見えになってしまうこともあります。さらに、ユーザビリティにも影響を与えますので、それを踏まえ、顧客、事業者の両方にどのくらいメリットがあるか評価して決めていきます。
成長フェーズ等で、好ましい機能や選択肢は違う
成長段階によっては、わかりにくいと思われ一時的に離脱が増えるにしても、あえて機能や選択肢を追加し、顧客の支持を増やしていくこともあります。ある程度成長した後は、これまで取り逃していたような顧客や売上を取り込むために、利用数が少ないかもしれない決済方法等を追加することもあリます。これは、売上増がユーザビリティの低下をカバーするかで判断します。顧客の練度にもより、不満は出るかもしれませんが、既存顧客が定着している場合、それほどインパクトはないと思いますので、ポジティブに考えてもよいでしょう。まずいのは、実施側が追加したらユーザビリティ、コンバージョンが下がると知らなかったという事態です。
開始時、立ち上げ時は、ユーザビリティは犠牲にせずに、利用比率の多いと思われる決済方法だけ最低限を提供し、顧客にサイトに慣れてもらい、状況も見ながら徐々に増やしていくという方法もあります。
冒険的に、流行りの機能や選択肢を取り入れる場合、その時は顧客からの支持があるように見えても、目指す顧客体験の実現に貢献しないものであれば、結果的に利用されなくなります。一時的なものだとわかったうえで、リソースを使ったとしてもメリットがあれば、成長期や成熟期等では採用されることもありえます。
決済方法をいくつ提供するか

決済方法は多いほうがコンバージョンは上がるといわれますが、あくまで、自社のコンセプト、客層、ビジネスモデル、成長段階、顧客の練度、状況により判断します。1つでは少なすぎても、10個では、決済フロー上でどう表現すればよいのか、悩みます。
選択肢の数とユーザビリティ
ユーザビリティの観点だけから言うと、最適な決済や配送の選択肢数は1つです。増えれば増えるほどわかりにくくなり、ユーザビリティは下がります。しかし、顧客が使いたい方法があることでコンバージョンには貢献します。サイトを企画、改善するときは、このバランスで最適数にする必要があります。
サイト上の説明文
機能や選択肢が増える、サイトが複雑になると、サイト上に説明をしっかり書き解決しようとします。ユーザーにわかりやすくしようという意図だと思いますが、実際は、説明文が増えるほど、ユーザビリティは下がります。ごちゃごちゃして、次に何をするか、どこに何があるかが直感的にはわかりにくくなるからです。さらに、多くのユーザーは、説明が多くなるほど読まなくなります。最近のサイトはやたら説明、トラブル防止のための但し書きをいれることが多くなっていますが、本来のコンバージョン、売上には貢献しません。本来、誘導や喚起であれば、色、文字、アイコン、レイアウト等クリエイティブの微調整、サイトの作り、短いインストラクションで解決すべきものです。誤解をおそれずに言ってしまうと、エクスキューズのためのことで、トラブル時の免責、または顧客への言い訳ができるためにやっていることと思えます。しかし、実際に何か起きたときにだけ対象者に説明すれば解決するような事柄も多く記載されていいます。本当に記載がなかったらどうなるのかや、文字の過多でのコンバージョン減と何か起きたときの対応リソースの比較で、本来は決めるべきものでしょう。
特に決済フローには、独自性や差別化は不要。それよりも
購入/決済フローは、消費者が慣れているフロー、レイアウトがよく、オリジナリティや差別化は不要です。そして、「支払いページ」での決済方法の提示方法は以前からよく議論に上がるところです。まずは、直感的にわかりやすいことです。次は、支払い方法の提示順番です。
顧客の利用の多い方法を上位に、そして、デフォルト化する
ユーザビリティの観点で離脱を減らすのであれば、先に述べたコンセプトや顧客の想定から、もっとも利用されている、または、されると想定したものを一番上に、そして、大きなスペースで、できれば、デフォルトの選択にしておく等でしょう。デフォルト設定は、システム的には簡単ですが、やられていないサイトも見受けます。それ以外の方法を希望の顧客には手間ですが、デフォルトの決済方法の比率が高い場合には、それを超えて有効です。そして、決済方法数にもよりますが、利用数の順に掲載します。
筆者のかかわっていたECでは、自宅にいる時間の長いと思われる主婦がメイン顧客で、かつ、注文単価が高く手数料を負担していてもコスト的にもメリットの代引きを一番上に置き、デフォルト設定をしていました。入力の手間もかからず非常に有効でした。また、注文が家族に知られることを嫌がるような場合(商材、購入頻度、金額等)では、コンビニ決済/振り込み、コンビニ/ロッカー受け取り等が好まれるため、上のほうに設置をしてデフォルト化していました。
とはいえ、意図的な表示の仕方も要検討
多少ユーザビリティは犠牲になるけれど、EC事業者側が顧客に利用してほしい順に掲載するということもあります。例えば、とにかくコンバージョンを上げるため入力項目が少ない決済方法を推奨する、在庫が少なく機会損失を減らすために、入金待ちをせずに注文確定と同時に支払が確定できるような方法、決済手数料や手間を考えての方法の推奨等もあります。個客目線ではなく見える場合もありますが、機会損失を避けるのと同時に、本当に欲しい顧客にできるだけ早く商品をお届けするといったフェアネスの観点からも、十分検討に値することです。
筆者がかかわっていた外資系の事業者では、財務の要請で決済手数料の最も安くなる決済方法を一番目立つところに配置し、デフォルトにしていくということもありました。
機能や選択肢の追加、終了
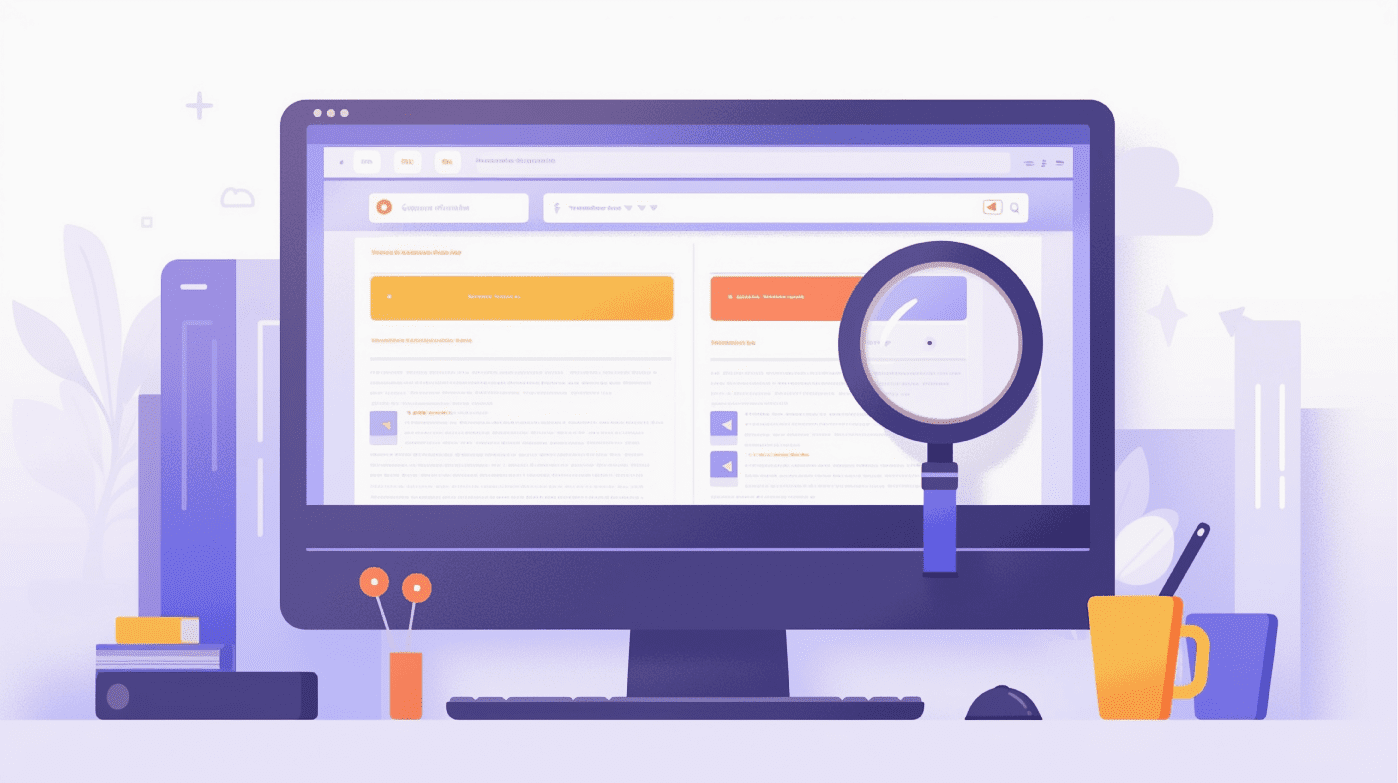
Webサービスですので、機能や選択肢を柔軟に変更するべきだという考えもあります。新しく出てきたものを早速導入し利便性を高め、使われないものは速やかに取り除きわかりやすく、また、他のものと入れ替える。やめてコストを削減し、その資源を他に回し、サービスを向上させる等ができます。
機能や選択肢の終了
ただ、どんな機能や選択肢も少しでも利用者がいる場合、安易には終了すべきではありません。少数かもしれませんが、なぜやめたのかという問い合わせも、お叱りもあります。やめる場合には、筆者も大変苦労しましたが、離反を招く顧客や弱者を顧みない「企業の論理」ととられることは避けたほうがよいと思います。そのためには、まず、安易にスタートしないということです。どんなサービスもなくなることで、サービスダウンと受け止められます。対応としては、継続性をちゃんと考えて開始する、やめる場合は終了までのリードタイムを十分とり、説明責任としてサイト上やメールにしっかり記載することです。いつの間にか終了させてしまうサイトをたまに見かけますが、顧客を大事にと言いながらいかがなものでしょうか。逆に、どんなに顧客に使われていても事業者側の都合でやめなくてはいけない機能や選択肢もあります。その場合も、しっかり説明責任さえ果たせば、筆者は、ずるずる引きずるよりはよいと考えています。
サービスアップの流れで顧客の支持を生み出す
機能や選択肢は、最小限で始め、だんだん増やしていくほうが、顧客のウケはよくなります。最初は機能不足等と不満があり、要望もでますが、ちょっとだけ我慢してもらい、ニーズの高いものから追加していきます。全般的にサービスがアップされていくように見えますし、顧客の要望に応えているようにも見えますのでサイトへの支持にも貢献します。また、どんどん改善、改良されている活発なサイトとみなされることもあります。
サイトオープン時に、機能や選択肢でもリスクはとらない
ECの立ち上げ時やリニューアル時の社内がバタバタしているときに、てんこ盛りの機能や選択肢を最初から提供してしまうと、運用が回らなかったり、思わぬ不手際等も起こりがちです。筆者は責任者として、大規模サイトを含む10回近くの立ち上げやリニューアルを実施し、何度も痛い目にあっているため、ミニマムな状態で、大々的な告知せずに行うソフトオープンを強く推奨しております。これは、運用、システムの不具合、セキュリティ対応のためでもあります。また、開発や実装は終わっていてもあえてサイトに表示させず、できるだけ最低限の機能や選択肢で開始し、安定運用になった際に、サービスインすることも勧めています。安全や信頼性確保に加え、これもサービスアップとして演出することで顧客への期待に応えたとも受け止めてもらえるからです。
まとめ
ECを成功させる場合は、ちゃんと考えたコンセプトが本当に必要です。そして、ユーザビリティを踏まえたうえで、成長ステージ等を鑑みて、ECビジネスとECサイトのサービス、機能や選択肢をコンセプトに最適化していくことが非常に重要です。長くECの立上げ、立て直し、成長に携わってきた筆者からの強いメッセージと取ってもらえれば幸いです。









