機会損失を防ぐ在庫発注方式の例
公開日:2021年04月01日
更新日:2021年04月01日
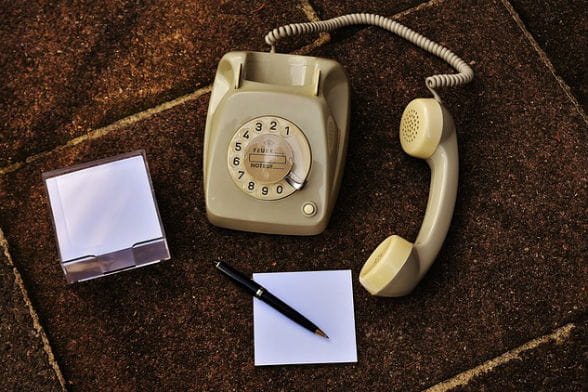
さまざまな種類の商材を扱う場合、仕入れを行う際にすべての商品を1つの方式で発注するのは合理的なやり方とは言えません。発注方式にはいろいろな方法があり、そのやり方を変えることで工数の軽減や在庫スペースの削減につなげることが可能となります。
欠品を出すことなく販売の機会損失を防ぐために知っておきたい在庫発注方式の例をご紹介します。
発注方式を効率化する目的
発注方式とは、製造業では部品や原材料を、小売業では商品を仕入れるために、いつ、どのように発注するかという発注の手法のことです。この発注方式にはいくつか種類があります。発注のために費やす手間とコストを考えると、商品毎の発注方法を変えることで効率化とコストを削減できる場合があります。
例えば商品の中には主力商品と、それ以外の商品があります。このうちあまり主力ではない商品についてしっかりと需要予測を立て、発注数量を決めて発注するといった労力のかかる作業を行うのは少々非効率的で、もう少しざっくりとした発注方式を採用するほうが合理的であるといったケースが多いです。
在庫管理はメリハリをつけて行うことが大切であり、商品毎に発注方式を選ぶことはそうした在庫管理の効率化・最適化をするために役立ちます。また、商品の販売実績や売れ行き傾向においてABC分析を行い分類した商品毎に発注方式を変えることで効率化・最適化が図れます。
代表的な発注方式
ではどのような発注方式があるのか、代表的な3つの方式を見てみましょう。
2ビン方式
ダブルビン方式、ツービン方式と呼ばれる発注方式です。この方式の考え方は次のようなものです。商品を2つの容器に入れ、片方の容器に入れた商品のみを陳列します。陳列した商品がなくなったら商品を発注し、もう一方の容器に入れた商品を陳列します。これを繰り返していきます。
2ビン方式のメリットは仕組みが簡単で、目で見て在庫の量がわかることです。デメリットは商品を保管するスペースが必要な点です。また場合によっては容器を3つや4つに増やすこともあります。
定量発注点方式
在庫があらかじめ定めた数量より少なくなると、一定数量を発注する方式です。発注する数量は毎回同じなのが原則。発注のタイミングは在庫がいくつになったら発注するかという「発注点」を計算して決め、ルール化します。
発注点=1日あたりの平均使用量×調達期間(リードタイム)+安全在庫
上の式の安全在庫とは安全を見越して余分に置いておく在庫の数量です。定量発注点方式のメリットは発注数量が同じなので事務処理が簡単なこと、デメリットは需要によって商品毎の発注点を計算する必要があること、売れ行きの波が発生した際に在庫の数量が多くなる傾向にあることです。また需要変動を考慮して定期的な見直しも必要です。
定期発注点方式
10日に1回、月に1回など発注間隔を決めて必要な数量を発注する方式です。発注数量はその都度、出荷数量を予測して決める必要があります。
発注数量=(発注間隔+調達期間)×需要量+安全在庫-現在の在庫量-現在の発注残
定期発注点方式のメリットは在庫を少なくできること、発注回数を減らせること、決まった時期に作業が発生するのでスケジュールが立てやすいこと。デメリットは需要予測が必要なこと、発注数量が一定でないため都度の事務(事後)処理が多くなることです。
発注方式の決め方
どの発注方式を選ぶかは、商材やターゲット(需要)の特性によって異なります。2ビン方式は単価の安い商品、あまり主力ではない商品に向いています。定量発注点方式も単価の安い商品、また需要変動があまりなく安定している商品向きの方式です。定期発注点方式は単価の高い商品、需要変動が大きい商品、そして主力商品など重要な商品に採用するのが適しています。
つまり発注方式の効率化・最適化には、販売側として商材やターゲットに関する的確な分析や深い理解が大きく影響するということです。
まとめ
発注方式を考えることは自身が販売する商材について深く考える機会にもなります。曖昧な感覚で進めるのではなく、商材ごとに最適な発注方式を選択して、効率的な在庫管理を実現してください。適正な在庫管理が行えるようになると、その分析結果は様々な機能改善に活かしていけるはずです。









